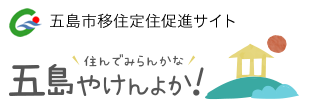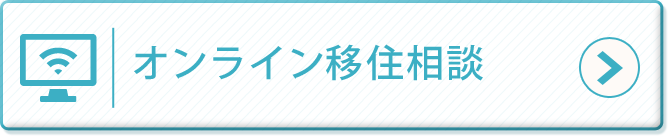地域活性化はなぜ必要?成功に必要なポイントと5つの自治体の成功例
更新日:2024年3月12日
ここ数年でよく耳にするようになった「地域活性化」という言葉。日本国内の各地域がそれぞれの地域を活性化させるために行っている取り組みの事を指します。この地域活性化を各地域が推進する事により、結果として日本全体が抱える悩みの解決に繋がる為、国を挙げて、各自治体と協力しながらおこなっている取り組みです。
この記事をご覧の方がお住いの地域でも「地域活性化」の取り組みを行っていたり、読んでいるご自身が実際に推し進めている担当者の一人だったりするかもしれません。
今回はそのような方のお力になるべく、「地域活性化が必要な理由」や、「地域活性化を成功へと導くポイント」についてお話ししていきます。
目次
地域活性化とは?

「地域活性化」とは、日本国内のそれぞれの地域の経済や社会、文化などの動きを活発化させる事です。その他にも、地域に住む人々の意欲を向上させることで、活気ある街づくりをおこない、それを維持・発展させる事を指します。
「地域活性化」が注目されるようになったのは2014年の第二次安倍内閣。「まち・ひと・しごと創生法」が定められた事がきっかけとなり、「地方創生」という言葉が認知されるようになりました。それに付随して地方活性化という言葉やその取り組みに注目が集まるようになったのです。
「まち・ひと・しごと創生法」は現在すでに廃止されていますが、国を挙げての地方創生の取り組みは類似した法案や戦略を基に引き続き推進されています。注目され始めてから10年が経とうとしている為、既に地域活性化に成功した自治体も多数あるというのが現在の状況。
現在はその成功例から学び、新たに地域活性化の取り組みを進めていく自治体が現れるという流れが出来ているので、地方活性化の為のUIJターン移住や地方都市での起業、街おこし協力隊への参加目的で短期移住などを考える若い世代も増えつつあります。地域活性化に明確な定義はない為、地域振興や街おこし、街づくりなどと同義語で使われることも多々あります。
なぜ地域活性化が必要なの?
国を挙げて取り組む「地域活性化」ですが、なぜそんなことが必要なのでしょうか。それには日本が抱える2つの課題が関係しています。
今の日本が抱えていて、「地方創生」で政府が解決(または緩和)しようとしているのが以下の2点です。
- 東京一極集中
- 地域の人口減少
この2点の解決には「地域活性化」が大きな役割を担っていると言えます。
どのような問題なのか以下で掘り下げていきましょう。
東京一極集中

東京圏に暮らす人の数は約3,600万人。これは日本の総人口のおよそ3分の1にあたります。東京圏には日本の政治の中枢となる霞が関や、日本の名だたる大企業の本社・本店があり、日本の生産力や経済力の中枢となっています。東京圏に一極集中させることで、大きなエネルギーとなり、日本全体の生産性の向上や経済の活性化に
繋がるのでは?と想像する方もいるかと思いますが、それも間違いではありません。
しかし、この東京一極集中により以下のようなデメリットがあるという声が多いです。
- 大規模災害時に国の機能が麻痺する
- 通勤ラッシュや交通渋滞
- 地方が衰退する
災害大国である日本では、どこで地震や津波などの災害が起こってもおかしくありません。もし仮に東京圏を中心にそのような大規模災害が起こった場合、政治はもちろんの事、大企業の中枢機能が麻痺してしまう可能性を持っています。
また、現在でも酷い通勤ラッシュや交通渋滞のある東京圏が更に活性化していくという事は、更に人口が増えるとどうなるでしょう。公共交通機関を使う人もさらに増えて、状況はますます悪化してしまいますよね。
地域の人口減少
前述の東京一極集中に付随するのですが、東京圏に人口が集まるという事は、地方から東京へ移り住んでいるという事です。これにより起こるのが地方の人口減少による衰退です。中でも働き盛りの若い世代が地方から東京圏へと移り住み、高齢化や慢性的な労働力不足へ陥っている地方自治体は少なくありません。
日本では現在、全国的に地方の転出超過や過疎化、超高齢化などが広がっており、既に全国で1799ある自治体のうちの約半数にあたる896の自治体が「消滅可能性都市」に該当するという状況に陥っています。
注)消滅可能性都市:地域社会や経済などを担う新しい世代が育たず自治体としての維持が困難となり、
無居住地化しなければならなくなる可能性が高い地域のこと。
これは「2040年までに20~39歳の若年女性人口が5割以下に減少する市区町村」のことを指し、2014年に『日本創成会議』で定義されました。
地域活性化は地方の衰退を食い止めるために必要
これらの状態を緩和または脱却する事が、政府と自治体が一丸となって地域活性化に取り組む理由です。
具体的な方法や成功例などは後述しますが、地方産業の活性化や雇用創出、住環境整備、東京圏からの移住支援などを主な活動としています。
各地方自治体での地方創生や地域活性化が成功していく事が日本全体の問題や課題を解決し、
若い世代が活躍できる豊かな日本へと向かう為の糸口のひとつとなっているのです。
地域活性化を成功させるために必要な3つのポイント

地域活性化という言葉からイメージする事と言えばどんなことがありますか?
なんだか突拍子の無いアイデアを掲げた街づくりで観光客誘致をおこなったり、住民へのサポートを他の自治体よりも手厚くして首都圏からの移住者数増加をねらったり、などという壮大な内容に感じてしまう人も少なくないでしょう。
しかしそんな大それたことよりも忘れてはならない大切なポイントが3つあります。
- 今ある地域の資源や特徴を活かす
- 長期に渡って持続可能な内容を考える
- 地域の人々を巻き込んで、たくさんの地域住人が参加できること
これらは斬新で革新的なアイデアよりも大切です。
以下で詳しく解説していきます。
今ある地域の資源や特徴を活かす
まず1つ目のポイントは、既に地域にある資源や特徴を活かすことです。活かす対象は人や物、事柄など何でも構いませんが、既にある人・物・事を活用する事で、自身の地域の独自性を出しやすくなります。
大枠は他の地域と大差が無くても、内容で差別化がしやすくなるはずです。
まずは地域にある資源やその特徴、自治体独自の長所などの再発掘から始めましょう。仮にその地域では当たり前とされている事でも、日本国内では極めて珍しい事がある場合もありますので、移住者や外部地域の人の意見を聞くのも良いかもしれません。その再発掘した物や事をそのまま活かしたり、新しい特産品や名産品を作る事で新たな販路を見出したり、地域産業の振興を目指すことができます。販路拡大は将来的に、雇用の増加や地域経済の発展にも繋がります。
長期に渡って持続可能な内容を考える
地域活性化は長期的に継続する事で、その効果を発揮する事ができます。
ですので、持続可能な内容を考える必要があるというのが、2つ目のポイントです。1つ目のポイントに沿って、どのような特徴が活かせるかがある程度決まったら、内容を詰めていきましょう。
持続可能な内容というのは、「何をやるか」だけでなく、そこにかかる費用や、取り組みを行う人員、組織構成など様々な事を考えなければなりません。例えば「月に1度ファーマーズマーケットを開催し、地元の名産品の認知度向上、地域外からの訪問者増を目指す」という内容だとすると、どこで開催し、どのような人に来てもらいたいのかという目標はもちろんの事、場所代や広告代、人件費などの支出を予測し、それを賄うくらいの収益を見込む為の計画を立てなければなりません。
地域の人々の善意や、ボランティアなどを頼りにした採算度外視のイベントだと長期的に持続することは難しいので、より現実的な計画を立てて準備を行う必要があるでしょう。
地域の人々を巻き込んで、たくさんの地域住人が参加できること
3つ目のポイントは最も重要と言っても過言ではありません。
地域活性化の取り組みは国や地方自治体の職員や有志が舵を取って進めていくケースが多いのですが、最終的には地域に住む一人一人が地域活性化の取り組みに参加できるように持って行くのが理想です。
なぜならば、地域活性化はその地に住んでいる人や関わっている人がより暮らしやすくなることや、その地域に住みたいと思う人を増やすことが目的なのですから。
ですので、まずは地域住民が取り組みに参加したい!と思えるような領域からアイデアを出してみるのが良いでしょう。例えば、子育てや仕事など、住民の生活に直接的に関わる領域です。自身に関わる事を通して行う地域活性化は、取り組みが成功した時にどのように変わるかが想像しやすいので、積極的に取り組みに参加しやすいです。
取り組みに参加する事が増えていくと、地域の人々の意識も良い方向に変わっていき、地域全体のムードもイキイキしたものに変わっていくでしょう。
地元住民に理解してもらうのも大切なポイント
地域活性化のアイデアを出す上で大切の3つのポイントは上記で解説しましたが、それらを遂行する為には住民の理解を得ることが絶対的に必要です。「地域の人々を巻き込む」と言う点でもお話ししましたが、地域の地元住民が置いてきぼりになってしまう取り組みでは、本来の目的とズレが生じてしまう為です。
極端な例えですが、若い世代の移住者増加を目的とした取り組みとして、若者向けの娯楽施設を増やし、高齢者向けの介護施設等の建設は後回しにすると、高齢者やその家族からの反発が強まりますし、逆に高齢者向けの福祉を充実させると若い世代の移住者増加は見込めません。
全世代にフィットする案というのは難しいですが、全世代が「地域活性化に取り組む事で生活が豊かになる」と感じられるように、取り組み案や目標、将来の画などが説明できる機会を設けたり、地域住民との繋がりの深い人物を地域活性化促進のチームメンバーとして採用したりなど、地域の人々も理解できる機会を提供すると良いでしょう。
地域活性化を成功させた5つの自治体の具体例
これまでお話ししたポイントを踏まえて、実際に地域活性化を成功させている5つの自治体をご紹介します。
内容や結果は様々ですが、以下でご紹介する自治体は、地域にある資源や文化財などを有効活用し、地域の人々を巻き込みながら地域活性化を推進しています。
【長崎県五島市】世界文化遺産×次世代テクノロジーで地域活性化
人口減少による活力低下が懸念されている長崎県では、各自治体がその対策に力を入れています。
そんな長崎県の中で、毎年多くの移住者を受け入れているのが、五島列島の中で最も大きな3つの島から成る長崎県五島市です。
島内には世界文化遺産の一部となっている重要文化財や関連する建物が多くあったり、いくつものテレビドラマの舞台としても取り上げられていたりと、観光資材が豊富。この様な背景から、移住者だけでなく旅行者の訪問も多い自治体なので、観光業も盛んです。
五島市の地域活性化の取り組みは、先代から受け継ぎ、守り育んできた島独自の文化や、歴史的な文化財を活かした観光客や移住者の誘致だけではありません。五島に住む人々がより住みやすく、若い世代が五島での明るい未来を想像できるような街づくりにも積極的に取り組んでいます。
街づくりの根幹にあるのは、日常生活に不自由しない商業集積や医療、教育面の充実です。離島での生活にはどうしても不自由さがつきものですが、その不自由さをカバーするために、市内中心部にはスーパーや複数の飲食店、病院やクリニックなどが揃っています。都会での生活と遜色ないという訳にはいきませんが、子連れ移住者やこれから子を産み育てる世代の方も安心して生活が出来る事が容易に想像できるでしょう。
それに加えて力を入れているのが、ICTやスマートアイランド構想。
五島では労働人口の減少や高齢化の対策として、次世代テクノロジーの活用に積極的に取り組んでいます。中でもよく知られているのが2022年5月から始まったドローンでの医薬品配送事業です。一般企業の協力のもと始まったこの事業では、往復約40kmの医薬品の配送を20~30分で完了させることができます。現在は五島市内のみでの試験的な運用ですが、五島での成果を基に配達範囲を広げ、日本全国の過疎地の医薬品運搬に役立てられるようです。
その他にもスマートアイランド構想の一環として、遠隔診療やスマート水道メーターによる水道の自動検針など、様々な実証に取組んでいます。
このような内容により、五島市は2021年までの移住者数は5年連続で200人を超えており、2022年は問い合わせだけでも500件を超えました。
【岐阜県東白川村】ホームページ活用で販路拡大。関連事業の売上増
岐阜県東白川村は岐阜県加茂郡にある人口2,000人強の村です。
村域の約90%を山林が占める東白川村は林業が盛ん。
この林業を盛り上げる事で地域活性化に成功し、村の森林組合木材出荷量が約48%増加し、建設業の売上は約70%増加しました。(平成21年から平成25年の販売推移データによる)東白川村が行ったのは、ホームページの活用です。自治体の中には多くの林業家や建設業を請け負う工務店がありますが、どこも個人経営のような規模で、各々が独自の繋がりを活かして商売を行っていました。
自治体ではこの地元の林業家や工務店に声をかけ、「地元産高級ひのき」を使用した注文住宅をホームページ経由で販売できるシステムを構築し、ホームページを開設。自由な住宅設計シミュレーションがホームページ上で可能となり、住宅建築の設計や見積りから建築、施工までをワンストップ処理で行うことを実現しました。村が仲介役となり一括管理する事で余計な手間やコストを削減する事ができる為、低価格での販売が可能となったようです。
このシステムがもっと広く周知されていけば、将来的には地元産の高級ひのきをブランド化させる事も難しくはありません。まさに自然豊かな田舎だからこそできる地域活性化の良い例と言えるでしょう。
【岡山県真庭市】林野の活用で林業・木材業の雇用創出に成功
同じ林業でも全く方向性の異なる取り組みを行った上で地域活性化に成功している岡山県真庭市もご紹介しましょう。
真庭市は岡山県の北部、鳥取県との県境に位置する市です。岡山県で最も広い面積を有する真庭市ですが、そのうちの約8割が山林。その為、前述の東白川村と同様に、林業やそれに関連する木材産業等が盛んです。その為、市の基幹産業となるのは林業や木材産業関係となっています。
自治体としては、この林業や関連事業の発展が地域活性化に繋がると考え、「真庭バイオマス発電事業」や
「木質バイオマスリファイナリー事業」、「有機廃棄物資源化事業」、「産業観光拡大事業」などを幅広く展開してきました。その中でもバイオマス発電事業が最もプラスに働き、年間約22億円の売り上げに繋がっています。事業が規模の拡大や売り上げ増により、林業・木材業関係者の50人程度の雇用の創出にも繋がり、地域貢献度もい結果を打ち出すことができました。
バイオマス発電とは、産業廃棄物となる間伐材などを活用した発電方法。林業の売上増や雇用創出以外にも、エネルギーの地産地消の促進、カーボンニュートラル社会への貢献など、様々な効果を生み出しています。現在は市内に2基のバイオマス発電機があり、市内のエネルギー自給率は格段に上がりました。将来的にはあと1基+メガソーラーの建設を行い、市内のエネルギー自給率が100%になる事を目指しているそうです。
地元の雇用創出や経済の発展に繋がる取り組みがSDGsにもうまく絡んでいるので、これから日本各地で同様の動きが出てきそうです。
【長野県東御市】特産品のブランド化で地域活性化促進
長野県東御市(とうみし)の基幹産業のひとつは農業で、中でもクルミやブドウの栽培に適した地形や気候です。
特産品のひとつにブドウがある事から、市内には小規模なワイナリーがいくつもあり、ワイン好きには魅力的な地域。そんな東御市では地域の名産品であるワインのブランド化を図る事で、地域活性化を促進させています。ブランド化をするにあたり、まずはブドウ生産量の増加と安定化が急務。その為にはブドウ畑の拡大を行うことが最初の一歩となりました。しかし地域活性化で地元農家や土地の所有者に大きな負担を強いるわけにはいかない為、日本政府の助成金などを活用しながらブドウ畑の規模を拡大しています。市内のブドウ畑は平成26年度には東京ドーム7.6個分(約36ha)に達する事を成し遂げ、生産量の拡大を現在も推し進めています。
また、東御市だけでなく近隣の市町村とも協力し、小規模ワイナリーの集積とワイン産地の形成も進めています。ひとつの市だけでなく、近隣の複数の自治体が協力する事で、一自治体の規模では成し遂げにくい事も実現できるという良い例です。
また、東御市だけでなく長野県全体で「長野ではじめよう じぶんSTYLE農業」と題し、県外の移住者の就農支援を行っています。労働人口が減っていく中で、他県と差別化を図った支援内容を実施し、新規就農者の獲得を目指しています。
【秋田県大仙市】駅前のリノベーションで歩行者数増加
秋田県大仙市は秋田県の南東部に位置する市で、人口は約75,000人です。
大仙市は全国花火競技大会(大曲の花火)の開催地であり、花火の街として知られている他、国指定の史跡(払田柵跡)など、歴史的な建物もいくつかあります。その為、県外から観光目的で訪れる人も少なくありません。
そんな秋田県大仙市では、JR大曲駅前のリノベーションを行って、地域の都市機能を駅周辺に集約させました。もともと大仙市は2005年に8つの自治体が合併してできた市ですので、合併後すぐは都市機能を持つエリアも複数存在していました。これを大曲地区に集約する再開発事業は、地域の利便性の向上や、住民活動の活性化に貢献する事が狙いです。
具体的には、商店街や商店などを集める事で駅前での買い回りを良くし、地域の中核病院や子育て支援に関連する施設などを駅周辺に集約させました。この地域リノベーションにより、商店街や各施設と地域住民が交流しやすくなり、地域全体に活気が出たとのことです。
この再開発事業では、当該エリアの歩行者通行量が増加する事を一つの目標にしていたようなのですが、
再開発後は目標の3,234人に対して3,762人と言う結果を出すことができました。
まとめ
この記事では地域活性化について、その概要や必要性、成功の秘訣などをご紹介しました。
地域活性化を成功させるために必要な事は「今ある地域資源を活かし、地域の人々と共に推し進めること」そして、「長期的に継続できる内容にすること」です。
地域活性化を進めるにあたり、一度ご自身の地域の特徴や資源を見直してみましょう。いい案が浮かぶと共に、あなたの住む地域の良さを再発見する事ができるかもしれません。
また今回ご紹介した「地域活性化を成功させた自治体」のひとつである長崎県五島市は、東京や大阪、福岡などで対面の移住相談会や移住セミナーを開催しています。生活環境やコスト面など詳しく知りたい方は、参加を検討してはいかがでしょうか。イベントの開催スケジュールは、離島移住促進サイト―住んでみらんかな 五島やけんよか!をご覧ください。
https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/index.html
監修
五島市UIターン相談窓口スタッフ(長崎県五島市地域振興部地域協働課移住定住促進班スタッフ)
関連リンク
- コラム|憧れの離島移住|人気の離島5選と離島移住を実現させるために押さえておきたいポイント
- コラム|島ぐらしを実現させたい!移住後の後悔を防ぐ事前準備やおすすめの離島
- コラム|島移住の不安を解消!移住者受け入れ環境や移住支援制度が充実している5つの島
- コラム|五島列島へ行こう!目的別おすすめスポット&アクティビティとご当地グルメ
- コラム|地方移住をはじめよう!メリット・デメリットや物件探しのポイント
- コラム|魅力あふれる地方移住!移住先選びのポイントとおすすめ都市ランキング
- コラム|憧れの田舎移住!失敗する原因と成功の為に押さえておきたいポイント
- コラム|移住前に絶対確認したい移住支援制度!支援が充実している自治体まとめ
- コラム|Uターン移住とは?メリット・デメリットや支援制度を徹底解説!
- コラム|離島への引っ越し料金の相場は?引っ越し時の注意点・おすすめ業者まとめ
- コラム|島への引っ越し料金を節約するには?方法と注意点を押さえて賢く引っ越し!
- コラム|今Iターン移住が注目されているのはなぜ?メリット・デメリットや人気の移住先をご紹介
- コラム|地方移住成功のカギ!補助金制度のある自治体と失敗しないポイントとは?
- コラム|新生活で必要なものは何?離島移住ならではの必需品もチェックリストでご紹介
- コラム|引っ越しに必要なものは何?手続きや引っ越し作業・初日に準備したいものを一挙紹介!
- コラム|田舎移住で憧れの古民家暮らし!メリット・デメリットや活用したい支援制度まとめ
- コラム|地方移住での仕事はどうする?地方での仕事の探し方や種類を実例付きでご紹介
- コラム|スローライフって何?田舎暮らしとの違いや地方移住で実現させるカギとは
- コラム|いま注目される二拠点生活とは?メリット・デメリットや費用、おすすめ自治体などを徹底解説
- コラム|二段階移住とは?魅力や注意点、失敗や後悔しないための秘訣
- コラム|単身での移住の魅力とは?メリット・デメリットや移住先の探し方を徹底解説